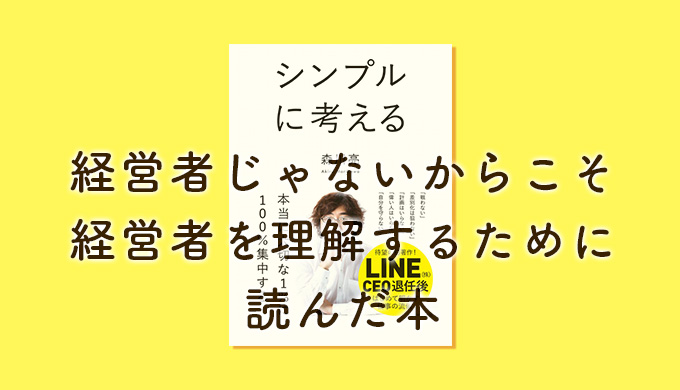
目次
経営者の頭の中をのぞきたくて、森川さんの「シンプルに考える」を読みました。
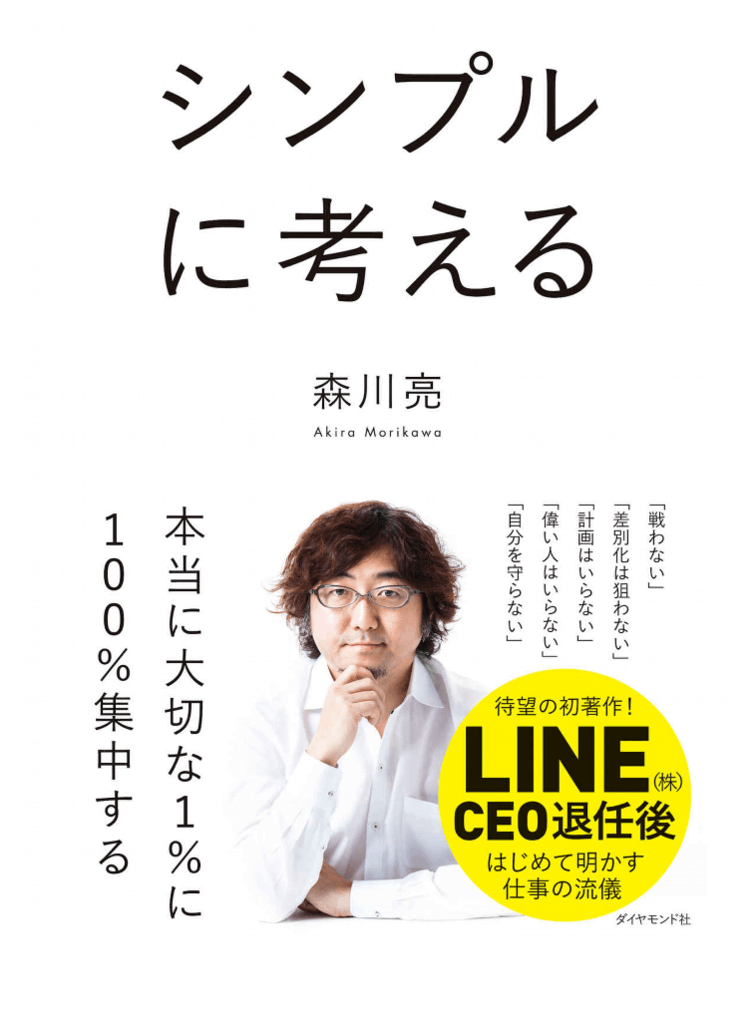
この本は、LINEの元CEO森川亮の経営術をまとめた本です。
私はこの時、社長とのコミュニケーションにとても悩んでいて、経営者が書いた本をたくさん読んでました。
経営者って、どんな基準で判断をしているのか。自分の動き方や、自分のつくるものには何が求められているのか。よくわからなかったのです。
経営者のように、お金や人を動かす職種と、デザイナーのように物を生みだすし職種では大切なことが違い、それによってすれ違いが起こることも少なくないのだと思います。
そんなときに、「ぷんぷん!」で終わるのではなく、経営者側の気持ちを知りたいと思ったのでした。
本を読むまでは頭硬そうおじさんという印象だった森川亮さん。
南場さん目当てに読んだのですが、「部下」という立場の私はちょっとがっかりする内容でした。
南場 学生さんと話していると、「自分が成長できる会社を選びたい」という人が多いんですよね。もちろん成長はすべきだと思うし、考え方としては間違ってはいません。けれども、入社初日から給料をもらっている以上、プロフェッショナルとして自分を追い込んで成果を出すのが第一にすべきことで。
森川 会社は学校じゃないですからね。「与えられる場所」ではないというか。
正直に言うと、自分も新卒の頃はよく「成長したい」という言葉を使っていましたが、どこか「上司や先輩が喜ぶおべっか」としての一面があったような気がして。
本心から思っていることであるけど、上司に喜ばれるし、真面目に見られるから言っとこう!みたいな。
だからこの記事を読んで、私は「若い子がぜんぶだめ。」とは思えなくてイラっとした。
むしろ上司という人たちだって「若い子の表面的な向上心を喜んで受け取ってるじゃん」というむなしさを感じたのでした。
経営者は、下の人間の気持ちなんてわかんなくなっちゃうのかな?悲しいな〜〜〜。と思いながら、ちょっと否定的な気持ちで読み始めたのでした。
森川さんは現場の視点(自分がわかる部分)と経営の視点(わからない部分)を両方大事にしている人だと感じた。
実際読んでみると、森川さんは「頭の固いおじさん」ではなかった!
森川さんは元々音楽をやっており、オーケストラで演奏するようにチームで働くにはどうしたらいいかという考え方を持っているそうです。
エンジニアやデザイナー視点でもビジネスを捉え、現場のパワーをどう活かすか考えている方と見受けました。
何よりも、「プロダクトが大事」と言いきっているシーンが多々あり、個人的にすごく嬉しかったです。
ものづくりを大事にしている経営者さんはひいきめに見てしまうぜ…。
「シンプルに考える」ぐさっときた部分の引用はこちら
・仕事は自分でとりにいく
・仕事はしんどくて当たり前
・自分の「感性」でいきる
・「空気」を読まない
・「専門家」にならない
・「確信」がもてるまで考え抜く
・「情報共有」はしない
・「クオリティ×スピード」を最大化する
経営者じゃない。デザイナーだけど、でも経営論を知っておく。
デザイナーは、経営者ともエンジニアとも関わる機会があり、両者の翻訳やつなぎ粉のような役割をすることが多い職業だと思っています。
私も板挟みになるシーンが増え「どうすればいいんだろ。」と自分を変える本を読むなどしたけど、あまり効果が出ませんでした。
なのでこういった経営者が書いた本を読んでいるのですが、
経営者ってこんなこと重要視してるんだ!こんなこと必要としてるんだ!
とインプットをするように。そこからちょっとずつ経営者がこんなことを考えているんじゃ。という仮説がたってきました。
「今、経営者から何が求められているのか。」
スピードなのか、クオリティなのか、プロジェクトマネジメントなのか。
「なぜ今、経営者はこのタスクを与えたのか。」
短期〜長期的な視点で経営を考えている経営者がなぜ今言いだしたか。を把握してないと、こちらもパワーの込め方が掴めなかったりします。
「そのデザイン作業にお金はちゃんとついてくるか。」
この世は資本主義とわかっていても、デザイナーにはお金にあまり興味がないタイプ(私も)もいます。
経営者は常にお金と比較して物事を考えることを知ることで、自分の作業時間がよりお金につながる動き方を意識するようになります。
要は経営者の考え方を知り、コミュニケーションをとることで、どういうデザイナーが必要なのか知ることがとても大事だ!と再認識した本でした。
まだまだ私は失敗ばかりですが(笑)めげずに頑張ろうと思います。
ベンチャー企業に勤めている方に、リンクする部分があってオススメ!
- 作者: 森川亮
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2015/05/29
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (6件) を見る
それでは〜がんばりまっしょい!^^
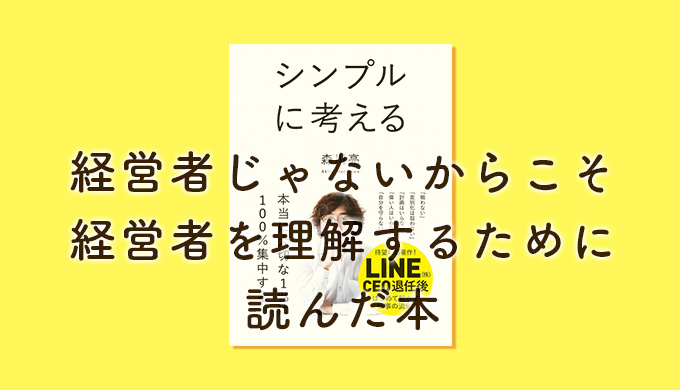



コメントを残す