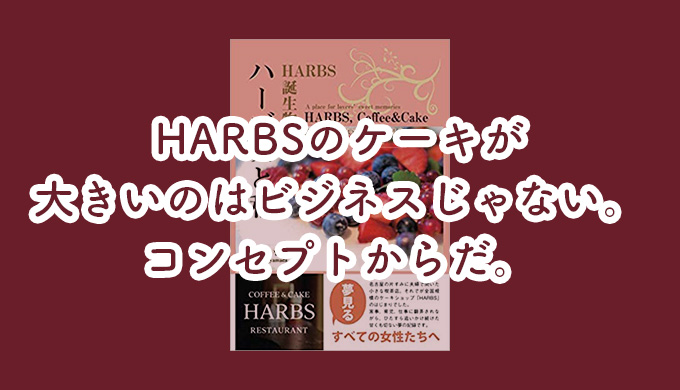
目次
めちゃデカ超うまHARBSのケーキからコンセプトの大切さ学んだ
ベンチャー企業にいると、経営陣と距離が近く、ついついお金がちゃんとまわるか、とか、合理化、生産性アップとか、数字のこととか、プロダクトの周りの流れに意識が行ってしまいがち。
つくり手がそういう意識を持つことは良いことだし、知ることや勉強することは大事なのだけど、一周回って私の仕事とは「自分が作るもののコンセプトを組み立てること。」「組み立てたコンセプトを純粋に追うこと。」だと最近感じています。
話が変わって、最近HARBS「ハーブス」のケーキを初めて食べて、すごく感動したんです。
まず、見た目。すごく大きくて、インパクト大。
そしてどのケーキも、とってもかわいい。
さらに口に入れると思ったより甘さが控えめで、最後まで楽しめることに、感動しました。

HARBS「ハーブス」のケーキを食べたことがない時は、こんな大きなケーキを売っているファンシーなお店に、カップルが列を作って並んでいることが信じられませんでした。
「女の子に、無理やり誘われているんだろうなあ。男の子、がんばれ!」と心の中で思っていたくらい。笑
でも実際は、あっさりした甘味なので、これは男の子も美味しく楽しめるなあ。
男の子もHARBS「ハーブス」のデートを楽しんでいるんだなあ。と素直に思えたのです。
どうやってHARBS「ハーブス」が生まれたのか気になったので、本を購入して読んだところ「いいサービス」を作るためには、「いいコンセプトを貫き通す」ことが大切なんだなあ。と自分の仕事に重なる発見がありました。
HARBS創業者が書いた「HARBSと私」あらすじ
HARBS「ハーブス」は実は名古屋が発祥の地。(知らなかった!)喫茶店を営む夫婦が試行錯誤して生まれたお店です。
喫茶店を開くことを決めた夫婦が、東京で当時流行の「TOPS」や「WEST」などを巡り、そのエッセンスを元にして、「メルローズ」という喫茶店をオープンさせます。
喫茶店をやるにあたって、私たちには、共通したテーマが一つだけあった。それは、近所のサラリーマンのランチをあてこんだ店にはしないということだった。できれば、恋人同士が遠くから車で来てくれるような店にしたいと思っていたのだ。今から思えば、夢というよりは妄想に近いような話だと思う。
当時、名古屋の喫茶店で本物のアメリカンコーヒーを出している店はなかった……。たぶん。
私たちは、本物のミディアム・ローストのアメリカン豆を仕入れ、それをドリップではなく、サイホンで一杯ずつ淹れることを店の基本にしたのだ。
・・・(中略)・・・
何かをやろうと思った時に、自分にその技術や知識が乏しいからといって、悲観する必要はまったくない。自分には勝負できる手札がないと嘆く人に限って、自分の持っている切り札に気がついていないことが多いものだ。まずは自分を冷静に見つめ、そして自分が挑もうとしている分野のライバルたちをたくさん観察することだ。そのとき、生半可な専門知識はかえって邪魔だ、お客の視点で純粋にその店を楽しめばいい。
メルローズが大人気店となった後、喫茶店のマスターから、社長になりたいという旦那さんの希望に答え、第2号店をオープンすべく、再び東京に足を運び、喫茶店を巡ることに。
共感できるヒントを掴み、それを真似する。けれど、私自身も実際の商品やサービスにつなげる試行錯誤はそこから始まるのだ。だから、東京に来て、喫茶店や飲食業界に限らず、いろいろな店を見て回った。客商売というものの本質について、どんな考え方があるのかを学びたかった。
そうして、2つの喫茶店は順調に売り上げを伸ばし、新しい店員や協力者も加わりHARBS「ハーブス」を誕生させる運びになります。
最初は全く売り上げの立たなかったHARBS「ハーブス」も、目玉商品「ミルクレープ」の開発から、大人気店へ。

HARBS「ハーブス」のミルクレープ、美味しいですよね。迷ったら必ず頼んでしまいます。
しかし、客足が途切れないHARBS「ハーブス」の経営に追われる中、売り上げの落ち込んだ「メルローズ」改装に踏み切るのですが、お客さんは集まらず、大失敗に終わってしまいます。
そんな中、友人との食事中にふと、「コンセプト」の大切さを再び認識させられることに。
あるとき、話が店の経営のことになった。良平さんが経営している店は、いわゆるセレクトショップである。彼が良いと思うものを仕入れて売っている。メーカーではない。けれど、限りなくブランドに近いものを感じる。それが魅力的だし、不思議だというと、それはたぶん、自分の「思い」が、店を貫き通しているからだろうという答えが返ってきた。つまり、コンセプトだというのである。店のコンセプトに惹かれてお客さんはやってくる。
その話を聞いた瞬間、私は頭の上に雷でも落ちたかのような衝撃を覚えた。ようやく自分の大きな忘れ物に気がついたのである。コンセプトこそが私たちの成功のもっとも根本であり、これまで私たちを支えてくれていたものではなかったか。
売り上げの落ち込んだメルローズに必要だったのは、「改装」よりも何よりも、新たな「コンセプト」だったのである。
コンセプトの重要性を実感した後、売り上げの落ち込んだメルローズは、当時話題になり始めていたニューヨークスタイルのカフェ「ニューヨーク・カフェ」として、名前も代わりリニューアル・再生。
再び人気店に返り咲きます。
その間も、HARBS「ハーブス」は店舗を拡大し、今のスタイルに。
ちょっと本筋からそれるのですが、HARBS「ハーブス」の大成功とは全く別のところで最後に落とし穴のように悲しいストーリーが語られているのですが、もし気になる方は読んで見てもいいかもです。
夫婦経営って、難しいな…と実感するような出来事でした。
HARBS「ハーブス」のケーキは、ビジネスシンキング主導ではなく、コンセプト・ファーストから生まれた商品でした。
そういう本を読んでから、HARBS「ハーブス」のケーキを食べてみると、確かになあ。と思うことがたくさんあるのです。
本の中にも、大きなケーキを生み出すのに試行錯誤したことが描かれているのですが、原価とか、手間とか、そういうものを一から順に計算していったら、あのケーキは生まれないだろうなあ。と。
最初に「恋人たちが楽しむ、大きなケーキ」というワクワクする、素敵なゴールがあったからこそ、それを実現するために試行錯誤し、手間や、原価のちょうどいいバランスがとれたのだろうなあと思いました。
「戦術」と「戦略」に「コンセプト」を追加できるように。
ビジネス第一主義の環境にいると、数字の目標と、どうやってそれを達成するか。という超合理的主義で動くことを求められるし、そういう振る舞い方がかっこよく見えます。
なぜかというと、数字で物事を判断するチームにいると、数字で話したほうが、スムーズで、早いんです。
だから、そういう環境に馴染むやり方を身につけたほうが、早い。
そういう環境で、正しいのか、正しくないのか、ちゃんと判断しづらい理想論のような「コンセプト」を切り札に話を進めることは、ほーんと難しいのです。
私も最初はコンセプトのような理想論ばかり提案していたので、全くうまくいきませんでした。
でも、なんとか環境に慣れた今も、あの頃提案していたことは、見当違いだとは思わないんです。
ただ、伝え方と、時期が見合ってないことに気づいていなかっただけ。
だからこそ夢のような話をして論破されると、「わたし全然合理的じゃない。」としょぼんとして、今は諦めようと思うことも多かったのですが、コンセプトの重要性に気づいたからこそ理想の形をはっきりと描き、ちゃんと伝えて、プロダクトに実現できるよう、そんな意味のあるトライをまた、してみなければ。と思っているところです。
日々のデザインのお仕事から気づいたことの記事
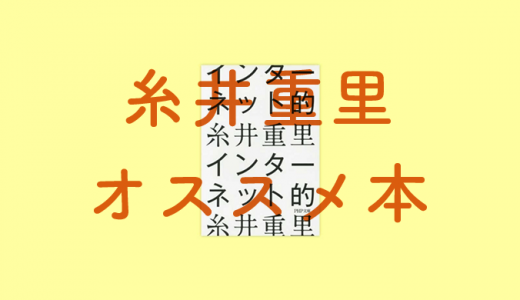 【14冊目】デザイン力だけじゃダメ。時代を読む力を持つ!「インターネット的」糸井重里
【14冊目】デザイン力だけじゃダメ。時代を読む力を持つ!「インターネット的」糸井重里
 【デザインの考え方】見た目が綺麗なデザインをデザイナーしか作れない時代は終わっている
【デザインの考え方】見た目が綺麗なデザインをデザイナーしか作れない時代は終わっている
 【よい展示】10年続く写真への憧れと苦しさと謎。十文字美信写真展「刻々」に行っての感想。
【よい展示】10年続く写真への憧れと苦しさと謎。十文字美信写真展「刻々」に行っての感想。
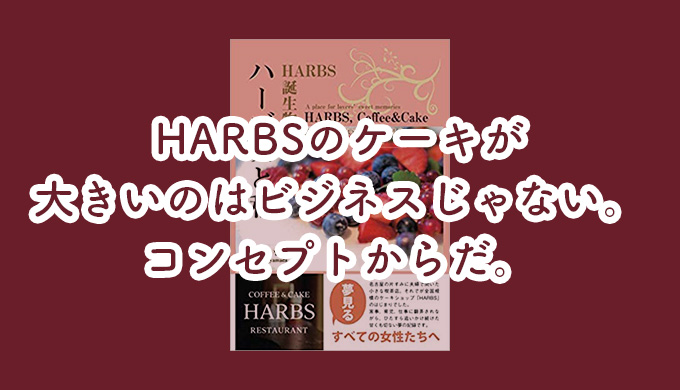

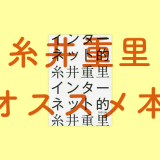
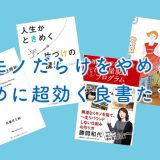
コメントを残す